|
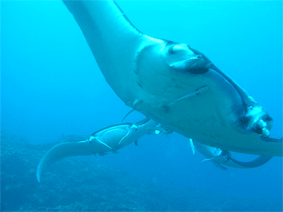 学名:Manta birostris Manta alfredi 1属2種 学名:Manta birostris Manta alfredi 1属2種
英名:Manta Ray
和名:オニイトマキエイ ナンヨウマンタ
沖縄名:ガマー、カマンタ
世界の通称:マンタ
ダイバー憧れのマンタは軟骨魚類で鮫の仲間であり、世界の約500種類とも言われているエイ類で最大の大きさになります!
2009年にはマンタ属1属1種から1属2種へと変わり、
和名でオニイトマキエイとナンヨウマンタの2種類となりました。
今後大西洋に生息するマンタの調査が進むと更に種類が増える可能性もあります。
特徴
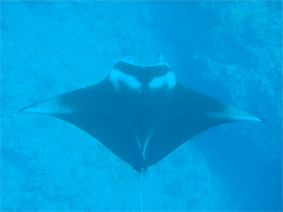 体型は菱形で体長より体幅の方が大きく、上部(背中)は黒、下部(腹)は白く個体ごとに違う黒い斑紋がある、斑紋のない白い個体や希に真っ黒な個体もいます。 体型は菱形で体長より体幅の方が大きく、上部(背中)は黒、下部(腹)は白く個体ごとに違う黒い斑紋がある、斑紋のない白い個体や希に真っ黒な個体もいます。
頭部に2つの頭鰭(トウキ、トウビレ)があり、眼は頭鰭の根元外側にあります。
移動中は外側に丸めて尖らせて抵抗を減らし、ホバーリング中や捕食中は開いてバランスをとったり、補食の補助を行います。
口は頭鰭の間にあり閉じているとき間は真一文字ですが最大に開くと
円形状になります。
背鰭が一つ棒状の尾が一本あり、鮫などに噛まれて欠落してるマンタも多数います。
鰓(エラ)は下部に5対ありクリーニング中などはワケベラなど掃除を行う魚が出入りをしています。
オニイトマキエイとナンヨウマンタの見分け方
オニイトマキエイとナンヨウマンタは外観での違いは背中の白色部の角度や5番目の鰓孔下の斑紋と
口回りが黒色であるかで判る様ですが、顕微鏡での皮膚の違いや歯の形状が確実に判るようです。
生息範囲
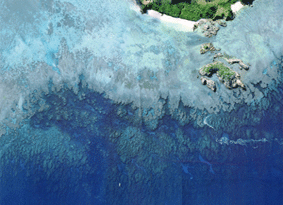 オニイトマキエイとナンヨウマンタは生息範囲(移動範囲)が違う様です。 オニイトマキエイとナンヨウマンタは生息範囲(移動範囲)が違う様です。
ナンヨウマンタは沖縄、九州以南の全世界の温・熱帯海域に生息しています、地域型で特定の範囲を回遊しているようです。
オニイトマキエイも基本的にはナンヨウマンタと同じ範囲に居るようですが更に外洋、北の寒い地方まで回遊しているようです。
川平石崎で確認されているマンタはナンヨウマンタでハッキリとした
オニイトマキエイは確認出来ていません、ハイブリッドらしい個体は
居るのですが・・・
川平石崎では日中が良く観られるのですが、朝やって来る方向や3時以降に帰って行く方向があるので夜間は同じ所にも戻ってるのかも
知れません。実際の所、詳しい行動範囲はまだまだ不明です。
食事
大きな体と口をしていますが、決して威嚇や攻撃することもなく、ジンベイザメと同じように小さなプランクトンやオキアミのような小型のエビを食べています。
歯と言えないほどの細かい物が下顎だけにあり、捕食は水面付近で大きな口を開けて泳ぎながら海水と一緒に吸い込み、餌を濾して食べます。
海水を効率良く吸い込む為に頭鰭(トウキ、トウビレ)をうまく利用しています、石崎周辺で多くの
餌さがある場合は複数のマンタが一日中捕食を行っています!
個体識別
  
お腹の黒い斑紋や鮫の噛み傷、傷痕等にて識別が可能で石垣島川平石崎で確認した個体だけでも230枚を
越えています。
識別済みの個体には名前を付けて観察しています。
|